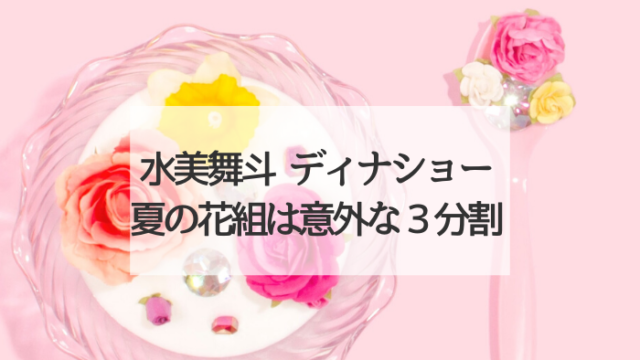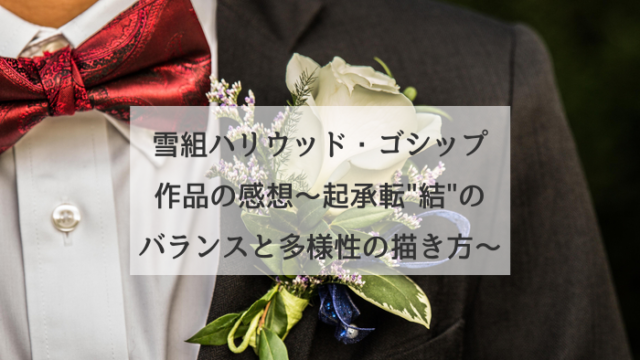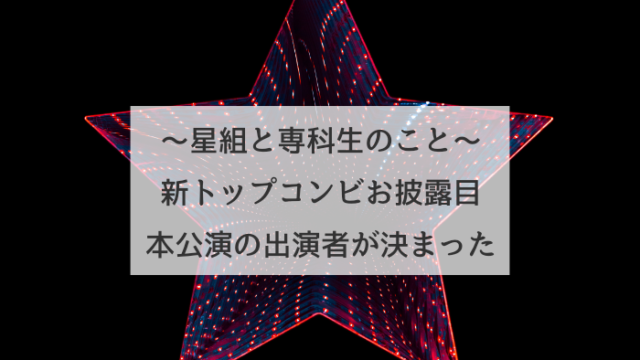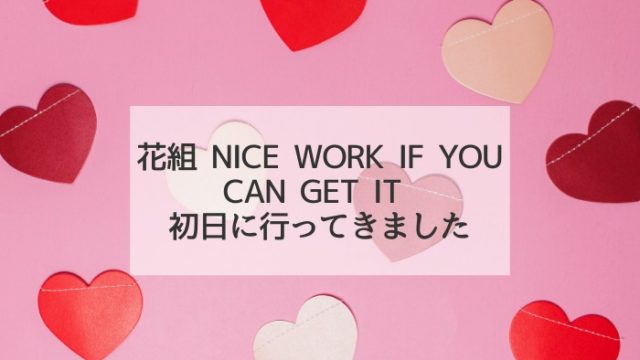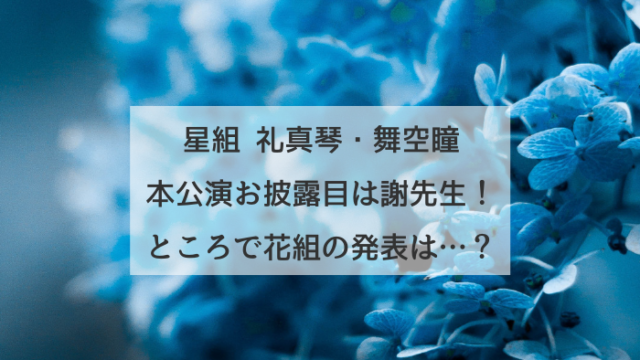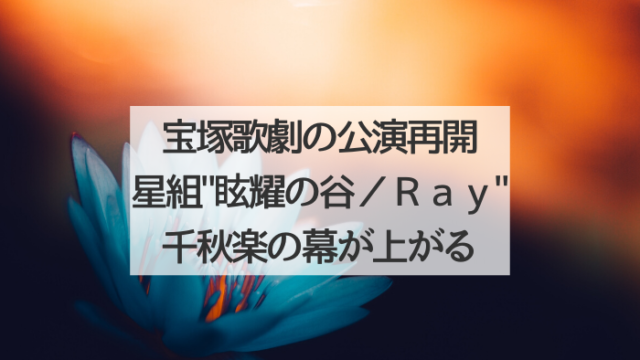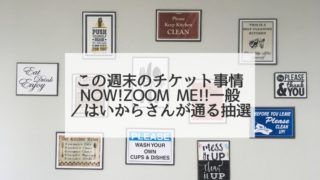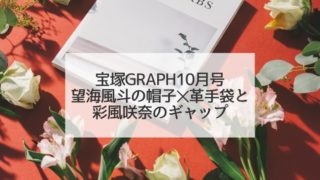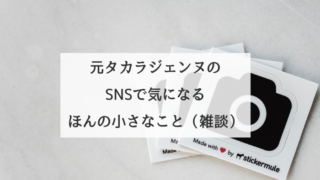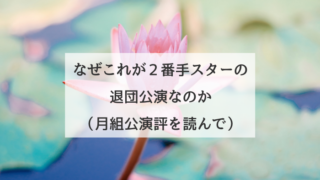こんばんは、ヴィスタリアです。
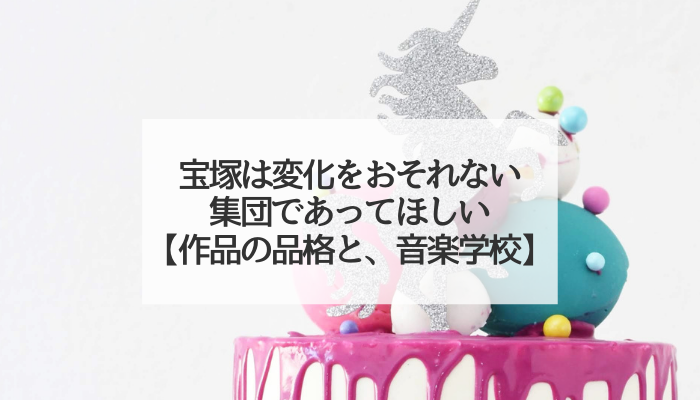
宝塚歌劇の品格 なにで笑いをとり、少数はをどう描くか
ライブ配信で「NOW! ZOOM ME!!」を視聴する前に拭いきれない不安がありました。
それは齋藤吉正先生、今回は大丈夫かな…ということです。
2019年の齋藤吉正のお仕事をヴィスタリアは許せていません。
贔屓の退団公演であった月組「夢元無双」の脚本が独り善がりなものであったこと、
花組「恋スルARENA」のセットリストが盛上りにかけるものであったこと。
特に横浜の歌メドレーは「なぜ横浜推し?」と思ったら先生ご自身が横浜の方なんですね(「NOW! ZOOM ME!!」のプログラムに書いておいでです)。
齋藤先生をお好きな方には申し訳ないのですがこれが正直な気持ちでした。
なので「NOW! ZOOM ME!!」での齋藤先生の仕事ぶりがどうなのか、タイトルを捻りに捻ったところで満足していないのかと
不安にならずにいられなかったのです。
そして不安は2幕冒頭の芝居で目の前に立ち上がってきました。
お好きな方、楽しまれた方もいらっしゃるかもしれません。
しかしこういう受け止め方をする者もいるということで正直に書きます。
テレビドラマのパロディも過去の雪組作品のパロディも凍りつきました。
一生懸命演じている舞台の上の生徒さんや楽しまれた方、お好きな方にはごめんなさい。
しかし自分はテレビドラマのパロディのどこがおもしろいのかまったくわかりませんでした。
そもそも宝塚歌劇に(たとえLIVEやタカラヅカスペシャルであっても)こういうコント、パロディ要素の強いものを求めていないというのもあります。
かなり尺が長くて30分近くあったかと思いますが、場面ごとカットして上演時間がその分短くてもよかったくらいです。
もし規定で時間を満たさないといけないのだとしても違う方法があったのではないか、
主演ののぞ様が大変なら下級生だけの場面があってもよかったのではないか。
そんなことを思いいました。
そしてこれだけなら笑いの感性の違い、宝塚歌劇に求めているものの違いですんだ話だと思いますし
こうしてブログで書くこともしませんでした。
しかしどうしても看過できないこと、記事にして残しておきたいことがありました。
それは笑いのネタが貧乏であったり純日本人やハーフという言葉であったことです。
これらで笑いが取れると平然と脚本にする感性はあまりにも鈍いし古いと思います。
他者が生まれたときから持っているもの、自身の力で変えたり選べないものを揶揄したり笑いにつなげる価値観に疑いを持たずに脚本にすることはやめてほしいですし、見たくありません。
小川理事長は今年の年頭会見で作品のクオリティと品格の向上を目標に掲げています。
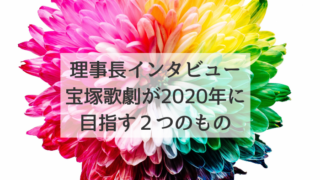
新作主義の宝塚歌劇で毎回良作を望むことは難しいのは体感としてありますが、
作品のレベルそのものの向上以前に校正をきちんとしてほしいと思っています。
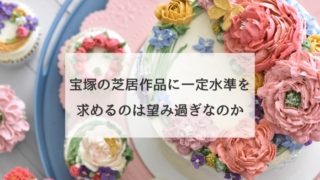
ここでいう校正は脚本そのもののクオリティの向上というよりも
ストーリーに矛盾はないか(ときにあきらかな矛盾があり客席で「???」となることもあります)、
そして人権上、あるいは社会的に守るべきものが守られているかといった
創作物として最低限クリアしてほしいことを想定して書いています。
今回の「貧乏」「純日本人」もそうしたチェックが入っていれば違う形の脚本になったと思いたいです。
また特に変わってほしいと思っているのが
性的であったり人種的であったり、生まれ持ったものや性的志向が社会的に少数の人物の描き方に
画一的な見方とその一方的な見方を笑いにつなげるような要素があることです。
そのような方法をとらなくても笑いは取れるし楽しい、感動的な舞台は作れるはずです。
オリジナル作品ではありませんが「I AM FROM AUSTRIA」で男性同士の恋と告白が自然に描かれたように。
オリジナル作品である「ハリウッド・ゴシップ」で黒人の男性(執事)が白人の男性(主人のゲスト)にタンゴを手ほどきするシーンがきちんと描かれていたように。
生徒さんは演出家の先生の本の通りに、指示の通りに一生懸命やるのが仕事ですから
この脚本についてのNOを言えるのは客席側にのみある権利であり可能なことのように思います。
なので自分はこのことについて客席なりライブ配信で遭遇すればNOと表明し続けます。
(もちろん宝塚歌劇以外の作品で遭遇したときもです。)
長い歴史の中で伝統をつなぎながらも柔軟に変化してきた一面がある劇団なのですから
いい方向に変化していってほしいと、少数派の意見かもしれませんが、願っています。
音楽学校もまた必要な変化ができる集団であってほしい
もう1つ変わる必要があるのなら変わることをおそれないでほしいと思っているのが音楽学校です。
先日音楽学校の規則の見直しについて報道があり当ブログでも触れました。
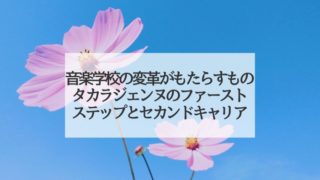
その後いろんな人がいろんなことを言っているなかで、東小雪さんが津田大介さんのインタビューに答えています。
東さんはご自身のブログにも記した具体的に予科時代に経験し、かつ本科時代に行ったことを語っています。
読んだときにインタビューを聞いたときも、事実はどうかは私は確かめようがありませんしここでは問いませんが、
よく聞く音校の厳しさとはこういうことなの?と信じたくない気持ちを抱きました。
報道を受けて学校側の言葉をこの記事で読みました。
物事は多面的に語られてほしい。
宝塚が「スパルタ不文律」を廃止 朝日新聞の仰天報道に困惑する音楽学校の言い分 https://t.co/ocDP6FHewT
— ヴィスタリア@聞いてちょうだいこんなヅカバナ (@zukabana_vis) September 20, 2020
音楽学校の内部でなにが行われているのか、事実はファンからは見えません。
また詳らかにされなくていいと思っています。
ファンが見るのは舞台ですから。
しかし劇団が伝統と変化の両面を持って続いてきたように、
音楽学校もまた残すべきよき伝統は継いでいきながら、芸事に直接関係のないパワハラと受け止められるような行為が本当にあるのだとしたら、
いい方向へ変わっていってほしい、連鎖を断ち切ってほしいと思っています。
またできると信じています。
なにをいいとするかを決めるのもまた学校であってファンではないですが「清く正しく美しく、そして朗らかに」に則しているか。
それに尽きるのではーーと感じています。
このことに関してはもう書くつもりはなく静かに見守るつもりです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
ランキングに参加しています。
ポチッとしていただたらうれしいです。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
![]()