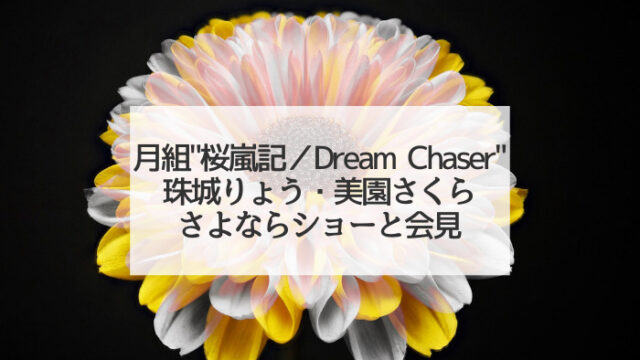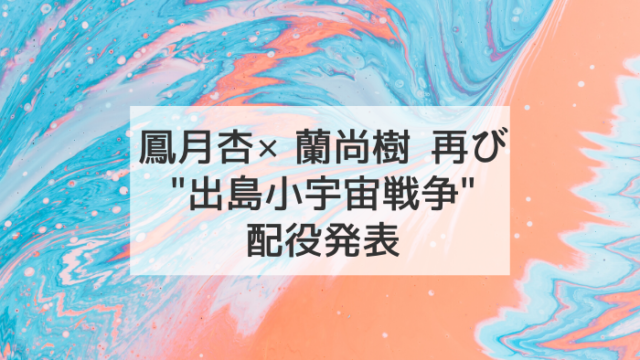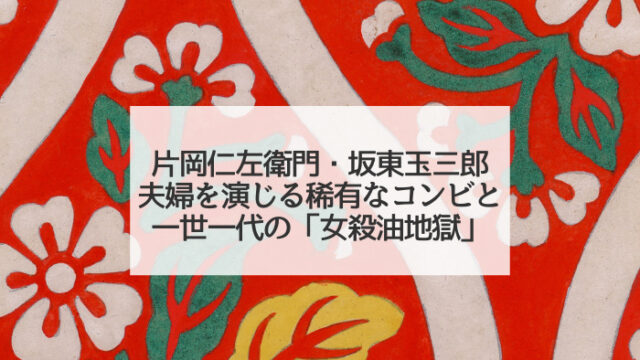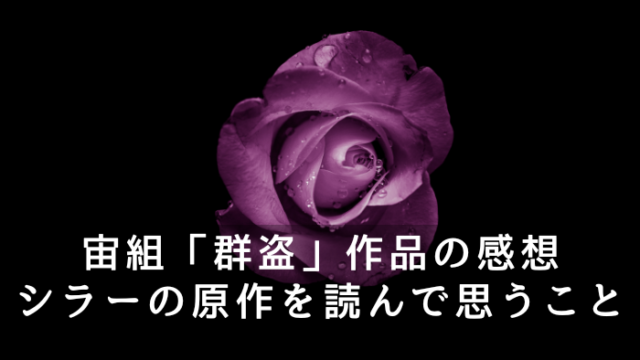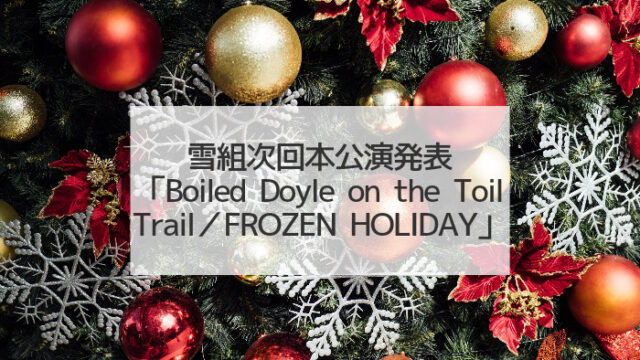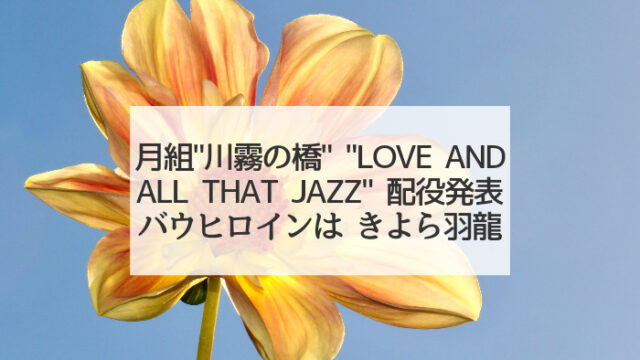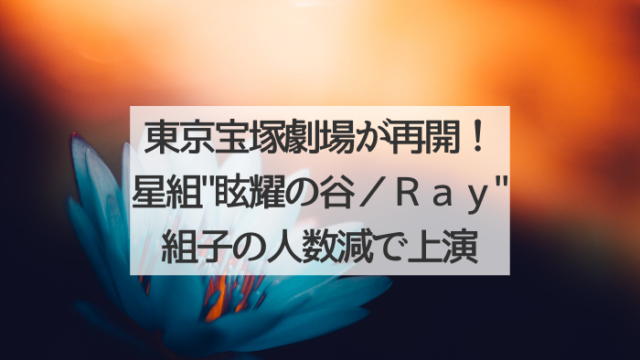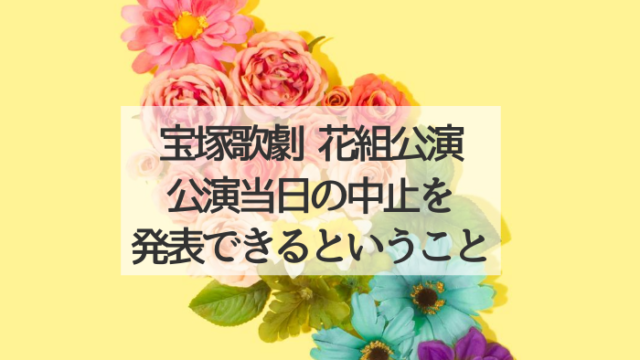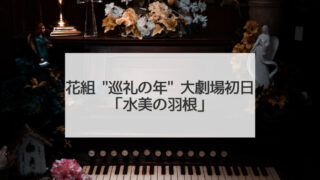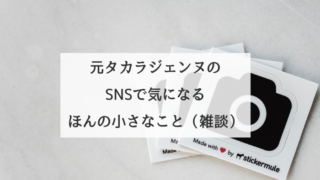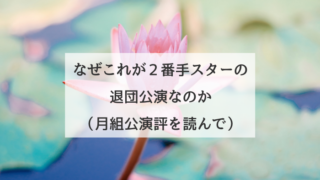こんばんは、ヴィスタリアです。
宝塚大劇場で花組「巡礼の年/Fashionable Empire」を観劇してきました。
ヴィスタリアの独断と偏見と偏愛に満ちた感想で、作品の内容に触れています。
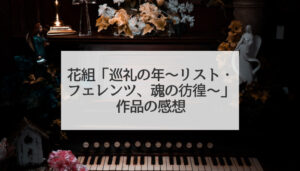
花組「巡礼の年」リストの生涯をたどり彷徨う物語
公式サイトの情報以外は特に予習をしないで観ましたが、リストの人生がわかっていると一層楽しめるのではないかと感じました。
「巡礼の年〜リスト・フェレンツ、魂の彷徨〜」はリストの内面に迫り、ときに精神世界(かどうかもわからない何処か)を彷徨いながらリストの生涯を辿る物語が展開していく作品だと、受け止めたからです。
現実のパリからジュネーブ、ウィーンへ、そしてリストが振り返る過去、そして魂の彷徨うどこかわからない場所――移ろいゆく場面の展開に生田先生の作品のおもしろさ、巧さが凝縮していると思いました。
盆を回しながらのセリ下がりでのスピーディな転換、
洗練されていてワクワクさせてくれる装置、
なにかを掻き立てる水の音、どれも秀逸ですし好きです。
19世紀ディスコとしか表現しようのないど派手なピンクの照明にミラーボールを回してのナンバーは衣装も過剰に豪奢で最高、
神童たちのピアノレッスンのナンバーは振付も新鮮で好きです。
歌も難しそうな曲が多いなあと思いましたが、マリー/星風まどかやジョルジュ・サンド/永久輝せあが台詞の延長から歌になるのが強く印象に残りました。
好きです。
リストやショパンが踊るキャラクターじゃないのに踊るところ、好きです。
場面の中で終盤に現実ではないらしい、どこかわからない場所でリスト/柚香光、ショパン/水美舞斗、そしてジョルジュ・サンド/永久輝せあが観念的に物語を展開させるのですが、
ここで語られることが非常によかったです。
リストがショパンに抱いた憧れとコンプレックス、そしてどんなに他者に認められて名声や名誉を得ようとも埋められないもの、自分が自分を認められないこと――自分で自分を許したり認めることの難しさは天才でなくともわかるのではないでしょうか。
リストとショパン、リストとジョルジュ・サンド、ショパンとジョルジュ・サンド、それぞれにしかわかり合えないものがあるのが伝わってくる場面でもあり、
たとえすべてが完全に理解できなくとも舞台ならこういうのもありだな…と自分は思いました。
生田先生の作品、好きです。
この場面が長くまた印象的なだけに、最後のマリーと再開する場面がやや唐突な感じがしたのですが、
作品がリストとマリーを描くことではなくリストの生き様を辿ることにあるのだとしたら、
二本立てだとこうならざるを得ないのかなと思います。
リストとマリーの再開まで20年弱という時間が経っており95分の中でそれを具に描き出すことはできないでしょう。
これはここまでに名前を挙げていない役たちにも言えることであって、
この公演で退団されるダグー伯爵/飛龍つかさ、ラプリュナレド伯爵夫人/音くり寿も歌などで活躍しつつも出番は前半に集中しています。
リストのライバルジギスムント・タールベルク/帆純まひろはじめ芸術家たちのグループも然りですが、本公演だとこうならざるを得ないのでしょうか。
95分で収めるには難しいであろうことは感じながらもまとめる工夫は場面転換のよさなどだけではなく、選びぬかれた台詞やエピソードも大いに効果的で心に強く残りました。
リストとマリーのすれ違いを示唆は非常に短いやり取りで効果的に表現されていました。
「(リスト)聞いたか」
「(マリー)素晴らしい演奏だったわ」
「(リスト)あの喝采を!」
また「王子様」というキーワードにまつわる印象的なエピソードもあり、長い年月を描いたものがダイジェストにならないフックとなっていました。
書いているうちに「巡礼の年」の感想というより生田先生の作品のどこが好きかになってきてしまいました。
それにしても、リストとマリーが鬼ごっこをして戯れている場面がありましたが次の「うたかたの恋」ではかくれんぼの場面がありますから、マリーという役名も相俟ってまるで予習のようだなあとも思いました。
初日と翌日に観たのですが、いずれの公演も台詞を噛んだり出が合わないといったことがあり、まだまだこれから作品が馴染んでいくんだろうな…と感じました。
いつもは東京で観劇するため新作をこんなに早い段階で観劇することがないからこそ感じたことでしょう。
次に観劇できるのは東京なので舞台がどのように変化しているのか楽しみです。
読んでいただきありがとうございました。
押して応援していただたらうれしいです。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
![]()